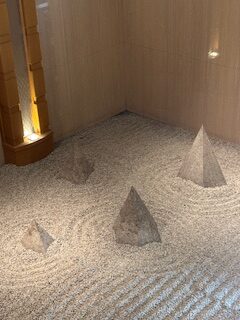管理職ー36 守備範囲
◆学校には、教育以外にも多岐に亘る仕事が押し寄せてきます。放課後の子どもたちの自転車の乗り方から通学路の植木の伐採や信号の設置など、実に多彩な内容が電話で要望されてくるものです。
これら全ての要望に応えようとして疲弊してしまう学校もあるようです。学校の守備範囲を広げすぎてしまった結果です。
私は、教職員が本来の教育活動に集中できるようにするためには、学校の守備範囲を明確にするべきだと考えています。私はよく野球に例え、説明しています。
「サードを守っているのに、ライトフライを捕りに行こうとしないこと。ライトフライはライトに任せればよいのです」
滑稽に思うかも知れませんが、実際に学校ではこのような無茶を行おうとして疲弊しているのではないでしょうか。
管理職は、目の前に出された要望を本当に学校の仕事なのか精査する。その後、学校の仕事でなければ、本来のポジションへ振り分けること。しかも良好な関係を保ちながら。ただ単に押しつけるだけでは今後の協力体制に支障をきたしてしまいます。
PTAや保護者の皆様へお願いするのか、地域の皆様へお願いするのか、教育委員会へお願いするのか、行政へお願いするのか・・・。
決して、要望をたらい回しにしようというのではありません。学校には、できることとできないことがあるのです。できもしないことを安易に受けることは、“親切が仇になる”、返って無責任な行為となってしまう可能性もあります。
学校本来の仕事を明確にすること。これも働き方改革の大事な眼目だと思います。