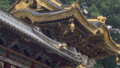学校教育ー70 授業研究
◆授業研究は、教師が意図するねらいを子どもたちがより理解しやすいように、工夫してその成果を検証する営みです。自分で授業をするのが一番勉強になるのですが、私のように授業から離れていると観点を決めて、授業を参観しながら勉強させていただくこととなります。
今日は、37本の研究授業を参観する機会に恵まれました。授業を参観していて気になったのは、発言も発表もしていない子どもたちが、授業中に何を考えているのか?ということでした。
教科の異なる全ての授業を参観している中で、発言も発表もしていない子どもたちに注目していました。すると、授業のことは全く考えていないと思われる子ども、一見、考えていないように見えても、きちんと授業に集中していて、いきなり手を挙げて答える子ども、様々でした。
音楽の授業では、グループ単位で指揮と楽器演奏を学習していたのですが、一人残らず学習に参加していることがよく分かりました。これは、実技を伴う教科の特性と言えるのかも知れません。
では、発言や発表もしていない子どもたちには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか?
以前、授業は教師と子どもたちとのコミュニケーションだと書かせていただきましたが、教師は、すぐに反応してくれる子どもたちだけでなく、全ての子どもたちに意図的に関わっていくことではないでしょうか。例え、反応が返ってこなくても機会ある度に関わっていくのです。やがて、その子どもが何を考えているのか、何となく理解できるのではないでしょうか。
反応がいい、発表を得意とする子どもたちだけを中心に授業を進めていると、流れはしますが、置き去りにされている子どももいるはずです。
授業はコミュニケーション、教師と学級全ての子どもたちとの間で、形は異なれど積極的に行われるべきではないか、そんなことを考えながら授業を参観し、自分なりに勉強していました。