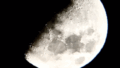管理職ー33 リーダーシップと父性
◆最近、周囲を気にするあまり、自分の思いを語るリーダーが少なくなったように感じています。家族の中では、父親が、職場ではリーダーが、自らの価値観を言い放つ場面が極端に少なくなってきたように感じているのは私だけでしょうか。
以前、林道義氏の『父性の復権』(中公新書)を読んだ時、ハンマーで頭を叩かれたような衝撃を受けました。自分が何となく感じていたモヤモヤ感が吹き飛んだのです。
父親は、家庭の中で自分の価値観を言い放つ、それが正しいとか正しくないとかではなくて、自分はこう思う、と語ることが大切なのに“友だちパパが多くなった”という内容が書かれてありました。
学校でも同じです。“○○ハラスメント”を意識して、教職員の機嫌を伺うような言動が多くなってきたような気がします。
「これをやりなさい」というのは、リーダーシップではなく、単なる押しつけです。
しかし、「私は校長として○○について、こうあるべきだと考えます。皆さんはどう思われますか?」と自分の思いや願いを言葉にすることは、学校という組織を束ねていく上で必要なことではないでしょうか。
そして、教職員が、話し合い、校長と異なる方法を選んだとしてもいいのです。そのことについて、校長がいつまでも引き摺らないことです。サッパリしたいものです。
校長が言うべきことも言わないで、はじめから「みなさんで、どうしたらよいか考えてください」というのは、一見、穏やかで物わかりがよい印象を受けますが、私は無責任な丸投げだと思います。
リーダーは、方向を示すことが仕事なのです。目指す方向を示す、その方向によっては、教職員と意見の食い違いだって生じることもあるでしょう。見ているもの、情報量が教職員とは異なるのですから当然です。それを怖れたり、自分が良く思われようと考えたりすることは、私の考えるリーダー像とは真逆の方向にあります。
方向性、価値観を大いに語る、仕事に対して、ロマンを語ると言っても良いでしょう。
その上で、自分の仲間である教職員のことを愛し、守り抜く人。
仕事に対して、人に対して、誠心誠意のベストを尽くす人。
これが、私の理想とするリーダー像です。
リーダーは常に悩みます。否、悩むからリーダーなのではないでしょうか。