 管理職
管理職 所属職員の見方 「教育は愛」No.312
校長や課長、部長という職を経験すると、多様な所属職員がいることを改めて実感します。時に、理に合わないことを見咎め、苦言を呈することもあります。称賛もできるだけ豊富にします。所属職員は十人十色です。
 管理職
管理職  生涯学習
生涯学習  教師
教師  教師
教師  学校教育
学校教育  生涯学習
生涯学習 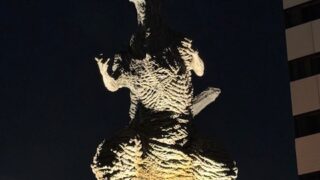 教師
教師  学校教育
学校教育  管理職
管理職  教師
教師