 教師
教師 愛する教師は愛される 「教育は愛」No.327
ある教師との会話です。「先生の愛が子どもに伝わり、子どもも保護者も先生のことを愛し、信頼してくれたのです」担任している子どもたち一人ひとりに惜しみない愛情を傾け、信念をもって教育している男性の先生です。その先生の愛が伝わり、いろいろな悩みを抱えていた子どもたちの心をポジティブに変容させてくれるのです。
 教師
教師  教師
教師  教師
教師  教師
教師 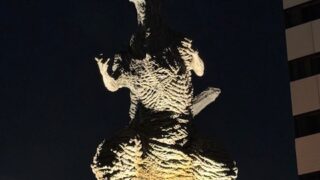 教師
教師  教師
教師  教師
教師  教師
教師  教師
教師  教師
教師